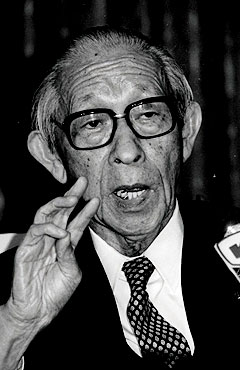自ら神話を崩して再出発する松下
2008.01.30 18:31
1/2
 |
|
「ああ、これは神のお告げか…」。
現在の松下グループの中で創業家の人間はわずか2人。 松下正治名誉会長と彼の長男・松下正幸副会長(62)だ。
松下の看板を下ろすことは、すなわち‘松下イズム’と呼ばれる幸之助の神話が終わることを意味する。 ただの社名とブランドの変更ではない。 ‘第2の創業’だ。 それで日本屈指の家電企業の松下内部はもちろん、日本財界が大きな衝撃を受けている。
▽‘幸之助’自尊心の終末
幸之助--。 彼は日本の近代化と高度経済成長を率いた指令塔だった。 また‘日本式経営’を導入した創始者だった。 1894年に生まれ、父の事業失敗で小学校を4年で中退した彼は、火鉢店、自転車店、電球会社など10年間ほど転々とした。
千辛万苦の末に得た2坪の電気用品店で彼は電球に使われる二股ソケットを発明した。 これがヒットして設立された会社が松下だ。 彼は会社を運営しながら、他の企業が従業員の労働条件や福祉にほとんど関心を向けていない点が気になっていた。
「これでは立派な企業をつくることはできない」。幸之助は離職率を下げ、組織への忠誠心を高めるため、年功序列制と終身雇用制を採択した。 企業優先価値の一も、二も、三も‘人’だというのが幸之助の哲学だった。 そのためか、彼の口癖は「松下は人をつくる会社だ。そして同時に家電もつくっている」だった。
幸之助は1927年、「日本全国民の必需品になるように」という意味で、自転車用のランプを‘ナショナルランプ’と名付け、これが大ヒットした。 その後、ナショナルは日本の国民的ブランドになった。 洗濯機から炊飯器、エアコンにいたるまで、すべての生活家電でナショナルは‘日本の自尊心’として根を下ろした。
幸之助が66歳だった61年、ナショナルブランドで米国に進出しようとした時のことだ。 ‘National’で商標登録をしようとしたが、すでにその名前は現地企業に使われていた。 やむを得ず北米対象輸出用ブランドとして導入したのが‘パナソニック’(Panasonic)だ。 パナソニックは‘あまねく(Pana)’と‘音(sonic)’の結合語で、‘あまねく(松下の)音が広がる’という意味が込められているという。
96歳の89年4月、肺がんで死去するまで、幸之助は5000億円の資産を築いた。 ‘経営の神’という称号も得た。 しかし彼がお金や名誉よりも重視したのは松下の自尊心だった。 それを示すエピソードがある。
がんで入院していた80年代後半、ある役員が病院を訪れた。 彼は思い切って幸之助にこう提案した。
「松下(社名)とナショナル(ブランド)はかなり古くなった。 社名とブランドを‘パナソニック’に統一しましょう」。幸之助はしばらく言葉を失い、顔をぶるぶると震わせたという。 その姿を見た役員は真っ青になり、すぐに病院を出て行った。 この噂が社内で広まり、松下という社名とナショナルというブランドは一つの聖域になった。 ブランドを統一しようという話を持ち出すことさえもタブーとされた。 これは幸之助の死後も続いた。
こうした状況で大坪文雄社長が電撃的に社名とブランドの変更に動いたのは「幸之助の郷愁に浸っていてはグローバル競争で後れを取り、生存自体が危うくなる」という危機意識からだ。 彼は「(松下)社員の努力は3つの名前(松下・ナショナル・パナソニック)に分散していた」と語った。
海外市場での勝負が会社の運命を左右する時代に松下の海外販売比率が50%にとどまっているのはブランドが分散しているからだ、というのが大坪社長の考えだ。 現在、ソニーの海外販売比率は70%、三星(サムスン)電子は80%に達する。
大坪社長の診断は統計に基づく。 米ブランドコンサルティング社‘インターブランド’の昨年の調査によると、パナソニックのブランド力は78位だった。 ナショナルは223位。 一方、社名とブランドが一つに統一されている競合他社は相対的に高いブランド力を見せている。 三星は21位、ソニーは25位、キヤノンは36位だ。
ブランド力が利益に占める比率などを勘案した‘ブランド価値’はもっと低い。 ソニーの3分の1にすぎない。 売上高が9兆1082億円と、三星に比べて2兆円も多い松下だが、時価総額では三星電子の60%にすぎないのはブランドの影響によるところが大きい、というのが専門家らの分析だ。
したがって松下の社名・ブランドの一本化は、すでに海外に定着している‘パナソニック’ブランドを通じて国際的なブランド力を強化しようという意図だ。 来年は海外売上高の比率を60%台に高める計画だ。
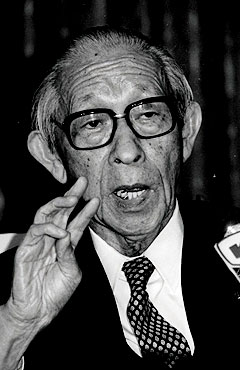 |
|
▽「創業家と決別して生き残り」
少数ではあるが松下に創業家の人がまだ健在する状況で、どのように経営陣はこうした決定を貫徹できたのか。 これには中村邦夫元社長(現会長)の力が働いた。
2000年に社長候補になった松下創業家の松下正幸を抑えて専務から社長に就任した中村は、‘破壊と創造’を旗幟に創業家との決別を果敢に推進した。 「職員を解雇してはならない」という幸之助以来の経営原則を覆し、2万人の従業員を整理した。
さらに幸之助が構築した松下伝統の事業部制を解体した。 徹底した成果主義で松下の実績をV字型に回復させた。 すでにこの時、松下の内部の雰囲気を‘幸之助ノスタルジア(郷愁)から抜け出してこそ生き残れる’という方向に変え、創業家との分離に成功したのだ。 そして昨年、社長職を最側近の大坪に譲った。
もちろん、幸之助が早くから唯一の息子を失い、創業家ではなく経営専門家の社長が5代も続いているため、松下という名前に特別な配慮をする必要がなかった、という分析もある。 見方によれば、今回の松下の社名およびブランド変更は時遅しという感もある。 すでに日本の電気・電子業界では社名とブランドを統一する動きが定着している。
ソニーは1958年に‘東京通信工業’から社名を英文‘SONY’に改め、海外での認知度を高めた。 TDKも83年、従来の社名の‘東京電気化学工業’から東京(T)、電気(D)、工業(K)という英文イニシャルの社名を付けた。
ニコンも88年‘日本光学工業’から海外で認知度が高いブランド名を付け、旭光学工業も02年にペンタックスに改名し、ブランド名と統一させた。
グローバル競争でどれほどブランドの存在が重要かというのは、ソニーの社長を務めた盛田昭夫と大賀典雄が「ソニーの最大資産は‘SONY’の4文字」と口癖のように話してきたことからも分かる。